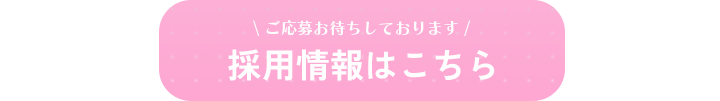コラム
遺品整理・生前整理で後悔しないための準備と手続き
生前整理 遺品整理
2025年4月25日
高齢の両親を持つ方、またはご自身が将来のことを考え始めている方にとって、遺品整理と生前整理は気になるキーワードではないでしょうか。
どちらも大切な作業ですが、その違いや具体的な手順を理解することで、よりスムーズに、そして安心した準備を進めることができます。
今回は、遺品整理と生前整理の違いを解説し、それぞれの作業内容についてご紹介します。
遺品整理と生前整理の違い
遺品整理とは何か
遺品整理とは、故人が亡くなった後に、残された家族や親族が故人の所有物を整理・処分する作業です。
住居の片付け、不用品の処分、重要書類の確認などが含まれます。
故人の思い出の品と向き合う作業となるため、感情的な負担も大きくなります。
遺族だけで対応が難しい場合は、遺品整理専門業者への依頼も検討しましょう。
生前整理とは何か
生前整理は、本人が健在なうちに自身の所有物を整理・処分する行為です。
老後の生活を快適にすること、そして、将来、遺族が遺品整理をする負担を軽減することが主な目的です。
自分自身で行うのが理想ですが、高齢などで困難な場合は、家族や専門業者に依頼することも可能です。
遺品整理と生前整理の違いを比較
主な違いは、作業を行うタイミングと、作業を行う人です。
遺品整理は故人の死後、遺族が行うのに対し、生前整理は本人が生前に自ら行います。
生前整理は、遺品整理の負担軽減を目的とするため、遺品整理を円滑に進めるための準備段階とも言えます。
遺品整理では、まず重要書類(遺言書、エンディングノート、預金通帳など)の確認が重要です。
その後、必要品と不用品を仕分けし、不用品の処分方法を決定します。
不用品は、自治体のゴミ処理ルールに従って処分するか、リサイクル業者に依頼するか、遺品整理業者に依頼するかなどを検討します。
生前整理では、不用品の処分に加え、財産目録の作成、デジタルデータの整理、遺言書やエンディングノートの作成なども重要です。
これらの作業を事前に進めておくことで、死後の手続きや遺族の負担を大幅に軽減できます。
遺品整理と生前整理をスムーズに進めるためのステップ
1:生前整理で準備しておきたいこと
・必要品と不用品を明確に仕分ける
・財産目録を作成し、定期的に更新する
・デジタルデータ(パソコン、スマートフォン、SNSアカウントなど)を整理し、必要なデータのバックアップを取る
・遺言書やエンディングノートを作成し、重要な情報を記載する
・家族に自分の意向を伝え、協力体制を築く
2:遺品整理で必要な手順
・遺言書やエンディングノートの有無を確認する
・重要書類や貴重品、思い出の品などを仕分ける
・不用品を処分する(自治体への廃棄、リサイクル業者への依頼、遺品整理業者への依頼など)
・住居の清掃を行う
・不動産の処分(売却、賃貸など)を進める
3:生前整理と遺品整理の費用について
費用は、作業内容、部屋の広さ、不用品の量などによって大きく変動します。
生前整理では、財産目録作成や遺言書作成などのオプション費用が発生する場合があります。
遺品整理では、不用品の量や処分方法によって費用が異なります。

まとめ
遺品整理と生前整理は、作業を行うタイミングと人が異なるものの、どちらも大切な作業です。
生前整理を適切に行うことで、遺族の負担を軽減し、円滑な遺品整理を進めることが可能です。
自分の状況に合わせて、必要な作業を計画的に進め、必要であれば専門業者に相談しましょう。
遺言書やエンディングノートの作成も忘れずに行い、大切な意思を家族に伝えましょう。
早めの準備が、将来の安心につながります。
故人の意思を尊重し、残された家族が安心して弔えるよう、計画的に進めていきましょう。