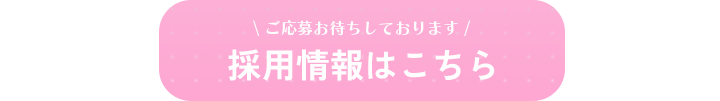コラム
一人暮らしの死亡手続きとは?スムーズな手続きのための準備と対策
遺品整理
2025年8月12日

一人暮らしの高齢者の方にとって、将来への不安は大きなものです。
特に、もしもの時に自分自身の手続きを誰がどのようにしてくれるのか、という疑問は、日々の生活に影を落とすかもしれません。
大切なのは、不安を解消し、穏やかな日々を送ることです。
この文章では、一人暮らしの方が亡くなられた後の手続きについて、必要な準備と共に、具体的にご紹介します。
目次
一人暮らしの死亡後の手続きの流れ
死亡の発見と通報
一人暮らしの方が亡くなられた場合、発見者はまず警察または救急に通報します。
発見場所が自宅であれば、管理会社や大家さんにも連絡を入れる必要があります。
その後、医師による死亡診断書(または死体検案書)の発行を受けます。
この診断書は、後述する死亡届の提出に必要不可欠です。
死亡届の提出方法
死亡診断書を受け取ったら、死亡した日から7日以内に、死亡地または本籍地の市区町村役所に死亡届を提出します。
死亡届には、故人の氏名、住所、生年月日、死亡日時、死亡原因などの情報が正確に記載されている必要があります。
必要書類は自治体によって異なる場合があるので、事前に確認することをお勧めします。
死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。
葬儀の手配と費用
死亡届の提出後、葬儀社に葬儀の手配を依頼します。
葬儀の規模や内容、費用は様々です。
費用については、事前に葬儀社に見積もりを依頼し、予算に合わせて計画を立てることが大切です。
葬儀費用は、国民健康保険や社会保険などに加入していた場合、葬祭費として一部が支給される場合があります。
相続手続きの概要
相続手続きは、故人の財産(預貯金、不動産、有価証券など)の相続に関わる手続きです。
相続人には、法定相続人が存在します。
法定相続人がいない場合は、相続財産管理人が選任され、手続きが進められます。
遺言書があれば、その内容に従って相続が進められます。
相続税の申告が必要な場合は、相続開始の日から10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。
各種契約の解約手続き
故人が契約していた賃貸借契約、公共料金、携帯電話、インターネット、クレジットカードなどの契約は、速やかに解約手続きを行う必要があります。
解約手続きに必要な書類や手順は、各契約ごとに異なります。
未払金がある場合は、相続人が精算する必要があります。

一人暮らしの死亡準備と生前対策
死後事務委任契約の重要性
死後事務委任契約とは、生前に信頼できる人に、死亡後の手続きを委任する契約です。
死亡届の提出、葬儀の手配、各種契約の解約など、多岐にわたる手続きを依頼できます。
委任内容や費用については、事前に委任者と受任者でよく話し合う必要があります。
遺言書作成のメリット
遺言書を作成することで、自分の財産をどのように相続させるかを明確に指定できます。
相続に関するトラブルを予防し、遺族の負担を軽減する効果があります。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言など、いくつかの種類があります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選びましょう。
財産管理の方法
一人暮らしの高齢者は、定期的に自身の財産状況を確認し、必要に応じて管理方法を見直すことが大切です。
預貯金の管理、不動産の管理、投資信託の管理など、自分に合った方法を選択しましょう。
大切な書類の保管場所
重要な書類(預金通帳、保険証券、印鑑証明書、マイナンバーカードなど)は、安全な場所に保管しましょう。
保管場所を家族や信頼できる人に伝えておくことも重要です。
連絡先リストの作成
普段から連絡を取り合っている人の連絡先をリスト化し、保管しておきましょう。
緊急時に備え、リストを複数作成し、異なる場所に保管しておくことをお勧めします。
まとめ
一人暮らしの死亡後の手続きは、死亡届の提出、葬儀の手配、相続手続き、各種契約の解約など、多くの項目が含まれます。
これらの手続きは、故人の意思を尊重し、円滑に進めることが重要です。
生前に死後事務委任契約や遺言書を作成しておくことで、家族や周囲の人々の負担を軽減し、自分の希望を叶えることができます。
不安を抱えている方は、専門家への相談も有効な手段です。
早めの準備と計画が、より穏やかな老後を送るために役立つでしょう。