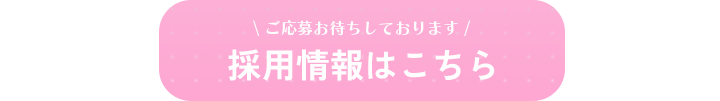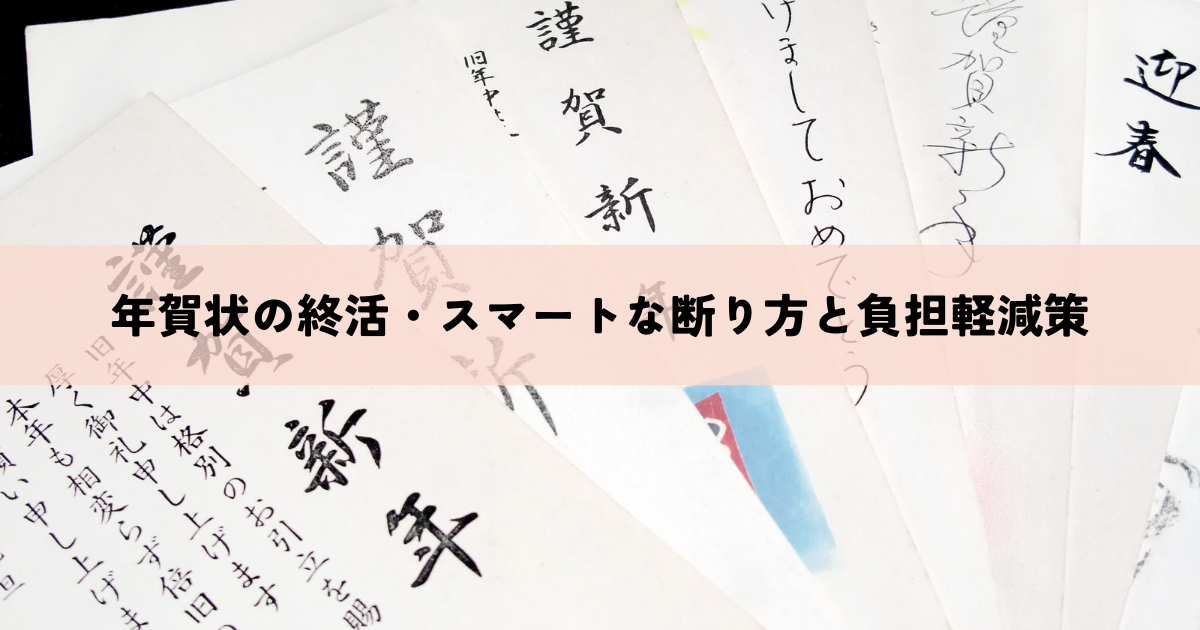コラム
生前整理での口座管理でスムーズな銀行手続きとは?
生前整理
2025年3月12日
生前整理は、人生の最終段階に向けて大切な準備です。
その中で、銀行口座の整理は特に重要な項目の一つと言えるでしょう。
多くの口座を保有している場合、管理が煩雑になるだけでなく、将来相続手続きにおいて家族に大きな負担をかける可能性があります。
また、休眠口座化による手数料発生や、預金保険制度の観点からも、銀行口座の整理は早めの対応が望ましいと言えるでしょう。
この記事では、生前整理における銀行口座の整理について、具体的な手続きや注意点、リスク回避策などを解説します。
目次
生前整理で銀行口座の整理で大切なこと
口座の現状把握と一覧作成
まず、保有するすべての銀行口座を把握しましょう。
通帳、キャッシュカード、オンラインバンキング情報などを確認し、銀行名、支店名、口座番号、口座の種類、残高などを一覧表にまとめます。
暗証番号は、安全のため記載せず、別途安全な場所に保管しましょう。
この一覧表は、家族にも保管場所を伝え、万が一の際にスムーズな手続きを支援します。
口座の使用目的(給与振込、公共料金支払いなど)も明記しておくと、整理しやすくなります。
不要口座の解約判断と手続き
一覧表を作成後、不要な口座の解約を検討します。
長期間利用していない口座や、利用頻度の低い口座は、休眠口座化による手数料発生や、管理の手間を考慮し、解約することをおすすめします。
解約手続きは、各金融機関の窓口で行い、必要書類(本人確認書類、通帳、キャッシュカード、印鑑など)を準備しましょう。
ネット銀行の場合も同様の手続きが必要となります。
解約前に残高を確認し、必要な手続き(引き落とし口座変更など)を済ませてから解約しましょう。
休眠口座化と口座維持手数料への対策
休眠口座は、10年以上取引がない口座で、預金が民間公益活動に活用される可能性があります。
預金は失われませんが、手続きに手間がかかります。
口座維持手数料も導入される可能性があり、利用頻度の低い口座は早めの解約が有効です。
定期預金は、必要時に引き出しにくい点を考慮し、普通預金への変更も検討しましょう。
家族への資金管理委任の方法と注意点
高齢化や認知症などにより、自身で資金管理が困難になった場合、家族に委任する方法を検討します。
キャッシュカードを預ける、家族名義の口座へ資金を移す、代理人カードを利用する、家族信託や任意後見人制度を利用するなど、いくつかの方法があります。
家族名義への資金移動は贈与税の対象となる場合があるので注意が必要です。
家族信託や任意後見人制度は、専門家のアドバイスを受けて検討しましょう。

銀行手続きにおけるリスクと対策
相続手続きにおける負担軽減策
相続手続きは、口座数が多いほど複雑で時間と労力を要します。
生前に口座を整理し、一覧表を作成することで、相続人の負担を軽減できます。
また、預貯金の状況を家族に共有しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
相続トラブル防止のための情報共有
相続トラブルを避けるためには、預貯金の状況や財産に関する情報を家族と共有することが重要です。
明確な情報共有により、誤解や紛争を防ぐことができます。遺言書の作成も有効な手段です。
預金保険制度と分散投資の重要性
預金保険制度は、銀行破綻時に一定額まで預金が保護されます。
しかし、一つの銀行に預けすぎると、この制度の範囲を超えるリスクがあります。
預金は複数の金融機関に分散させることで、リスクを軽減できます。
認知症や判断能力低下への備え
認知症や判断能力低下に備え、事前に家族信託や任意後見人制度などを検討することが重要です。
これにより、判断能力が低下した場合でも、財産管理を適切に行うことができます。
また、エンディングノートを作成し、自身の希望や財産状況などを明確に記しておくことも有効です。

まとめ
生前整理における銀行口座の整理は、相続手続きの円滑化、休眠口座や口座維持手数料への対策、家族への負担軽減、相続トラブル防止に繋がります。
口座の現状把握、不要口座の解約、家族への委任方法、リスクへの備えなど、この記事で解説した点を参考に、早めに対策を進めることをおすすめします。
複数の口座を保有している場合は、使用状況を確認し、整理・統合を検討しましょう。
また、預金保険制度を理解し、預金の分散も意識することが重要です。
万が一の事態に備え、家族と情報を共有し、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。