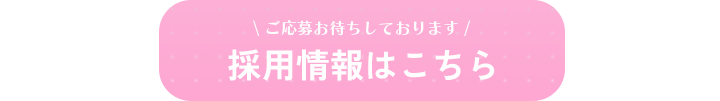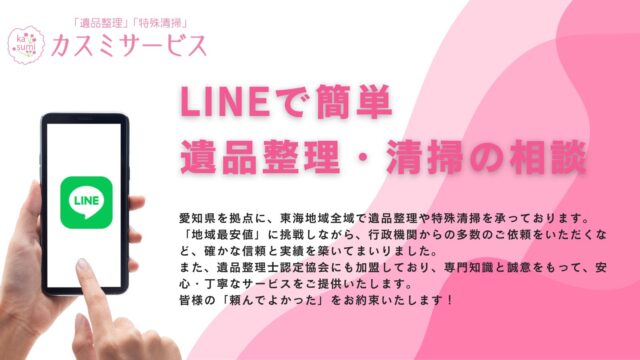コラム
親の死亡後やること・手続きの全容とスケジュール
遺品整理
2025年8月29日
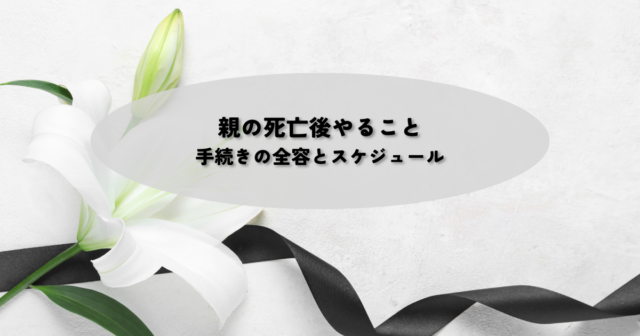
親を亡くした時、何をすればいいのか。
突然の出来事に、戸惑いと悲しみに包まれるでしょう。
多くの手続きが待ち受けており、何を、いつまでに、どのようにすれば良いのか、見通しが立たないかもしれません。
この先、どのような日々が待っているのか、不安を抱えている方も少なくないはずです。
今回は、親の死後、遺族が直面する手続きを、期限や必要な書類、手続き場所と共にご紹介します。
目次
親の死亡直後 何をすべきか
死亡確認と届け出の手続き
まず、医師による死亡確認が必要です。
病院で亡くなった場合は医師が死亡診断書を発行します。
自宅で亡くなった場合は、医師を呼んで死亡診断書を発行してもらう必要があります。
事故死や急死の場合は警察への通報が必須で、死体検案書が発行されます。
これらの書類は、後の手続きで必要となるため、複数枚のコピーを取っておきましょう。
葬儀の準備と執り行い
死亡確認後、葬儀社に連絡し、葬儀の準備を始めましょう。
通夜・葬儀の日程、形式、費用などを葬儀社と相談します。
故人の希望があればそれを尊重し、そうでなければ家族で話し合って決めましょう。
葬儀社は、会場の手配、祭壇の準備、その他の手続きを代行してくれるため、大きな助けとなります。
死亡届の提出と戸籍謄本の取得
死亡届は、死亡を知った日から7日以内(海外で死亡した場合は3ヶ月以内)に、死亡者の本籍地、住所地、または届け出人の住所地のいずれかの市区町村役所に提出します。
死亡届と同時に火葬許可証の申請も可能です。
戸籍謄本は、相続手続きに必要な書類です。
必要な枚数を取得しておきましょう。
必要な書類の収集と整理
死亡診断書、死体検案書、死亡届受領証明書、戸籍謄本など、今後必要となる書類を大切に保管しましょう。
これらの書類は、相続手続きを進める上で非常に重要です。
整理してファイリングしておくと、後々スムーズに進められます。

相続手続きのスケジュールとやること
相続開始と相続人の確定
相続は、被相続人の死亡によって開始します。
相続人は、民法に基づき、配偶者、子、父母など、法律で定められた順位で決定します。
相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
遺産の調査と評価
相続財産の調査を行いましょう。
預金、不動産、株式、保険金など、故人が所有していたすべての財産を洗い出しましょう。
それぞれの財産の評価額を算出する必要があります。
不動産の評価には、専門家の力を借りるのも良いでしょう。
相続税の申告と納税
相続税の申告は、相続開始を知った日から10ヶ月以内です。
相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合に必要となります。
相続税の計算は複雑なため、税理士に相談することをお勧めします。
遺産分割協議と手続き
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。
協議がまとまれば遺産分割協議書を作成します。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
不動産の名称変更などの手続きも必要です。
まとめ
親の死後、遺族は多くの手続きをこなす必要があります。
葬儀、死亡届の提出、年金関係の手続き、相続手続きなど、それぞれに期限や必要な書類、手続き場所が異なります。
このガイドラインを参考に、一つずつ確実に進めていきましょう。
必要に応じて、専門家のサポートを受けることも検討してください。
大切なのは、慌てず、一つずつ着実に手続きを進めることです。
悲しみの中での手続きは大変ですが、故人の思いを大切に、未来へ向かうための第一歩を踏み出しましょう。
関連記事
人気記事
各種カテゴリー
遺品整理
特殊清掃
ゴミ屋敷
生前整理
空き家整理
残置物整理