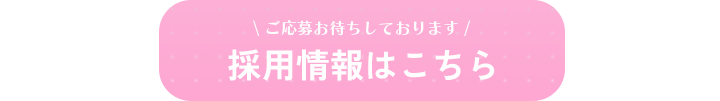コラム
遺品整理はいつから始めるべき?高齢者と家族のための適切な時期とは?
遺品整理
2025年4月29日
大切な人を亡くした後、残された遺品整理は、心身ともに辛い作業です。
いつから始めたらいいのか、何を優先すべきなのか、迷う方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺品整理の開始時期について、様々な状況を想定しながら、具体的な例を交えてご紹介します。
目次
遺品整理はいつから始めるべきか時期の選び方
1:葬儀直後から始めるメリット・デメリット
葬儀直後から遺品整理を始めるメリットは、相続人や親族が集まっているため、相談しながら進められる点です。
また、賃貸物件の場合、早期の退去手続きが必要となるケースもあります。
一方、デメリットとしては、悲しみに暮れる中で作業を進めるのは精神的に負担が大きく、集中できない可能性があります。
孤独死の場合や、相続人が遠方に住んでいる場合などは、葬儀直後からの開始が現実的かもしれません。
2:諸手続き完了後から始めるメリット・デメリット
死亡届の提出や年金・保険の手続きなど、諸手続きが一段落してから遺品整理を始める方が、落ち着いて作業に取り組めます。
時間的な余裕も生まれますので、自分たちのペースで進められます。
しかし、手続きに時間がかかると、遺品整理開始が遅れる可能性があります。
また、賃貸物件の場合は、家賃が発生し続けるため、早めの対応が望ましいです。
3:四十九日法要後から始めるメリット・デメリット
四十九日法要は、親族が集まりやすい時期です。
そのため、遺品整理や形見分けについて相談しやすく、合意形成がスムーズに進みます。
法要後であれば、気持ちの整理もつきやすいため、作業に集中できるでしょう。
ただし、法要までに遺品整理を完了させる必要がある場合は、時間との兼ね合いが重要になります。
4:相続税申告前までに終わらせる必要性
相続税の申告期限は、死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の申告には、遺産の全容を把握する必要があるため、相続税申告前までに遺品整理を完了させることが重要です。
期限に間に合わないと、ペナルティが課せられる可能性があります。
遺品の中に高価な品物がある場合、特に注意が必要です。
5:遺品の種類と量による開始時期の調整
遺品の量や種類によって、遺品整理にかかる時間は大きく異なります。
大量の遺品や大型家具がある場合は、時間と人員を確保する必要があります。
一方、遺品が少ない場合は、比較的短期間で整理できるでしょう。
作業前に、遺品の量と種類を把握し、必要な時間を見積もることが大切です。
6:作業者の人数と体力による開始時期の調整
作業者の人数や体力も、開始時期を決める上で重要な要素です。
高齢者や体力の弱い方が作業を行う場合は、無理のない範囲で進める必要があります。
複数人で作業すれば効率的に進められますが、人手が足りない場合は、業者に依頼するのも一つの方法です。
7:賃貸物件の場合の注意点
賃貸物件の場合、家賃が発生し続けるため、早めの遺品整理が重要です。
契約内容を確認し、解約手続きに必要な期間を考慮して、開始時期を決めましょう。
原状回復費用なども考慮に入れておく必要があります。
8:持ち家の場合の注意点
持ち家の場合は、空き家になることで、固定資産税の増加や、倒壊・火災などのリスク増加に繋がる可能性があります。
特定空家にならないよう、適切な管理が必要です。
遺品整理を始めるのが遅れるとどうなるの?デメリットを徹底解説
1:賃料や固定資産税の発生
賃貸物件では家賃が、持ち家では固定資産税が発生し続けます。
特に持ち家が特定空家と指定されると、固定資産税が大幅に増加します。
無駄な費用を避けるためにも、早めの遺品整理が望ましいです。
2:相続手続きや相続税申告への影響
遺品整理が遅れると、相続財産の把握が遅れ、相続手続きや相続税申告に支障をきたす可能性があります。
相続税の申告期限に間に合わなくなると、ペナルティが課される可能性もあります。
3:空き家によるリスク増加
空き家は、火災や倒壊、空き巣などのリスクが高まります。
近隣への迷惑や、相続人への損害賠償請求などのリスクもあります。

まとめ
遺品整理の開始時期は、遺品の量、作業者の人数、相続手続きの進捗状況、そして居住形態など、様々な要素を考慮して決定する必要があります。
早すぎるのも遅すぎるのも問題があり、状況に応じて最適な時期を見極めることが重要です。
賃貸物件の場合は家賃の発生、持ち家の場合は固定資産税や空き家リスクを考慮し、相続税申告期限も念頭に置いて、計画的に進めましょう。
遺品整理は、故人の人生を丁寧に締めくくる大切な作業です。
ご遺族の皆様が、落ち着いて作業に取り組めるよう、心から願っています。